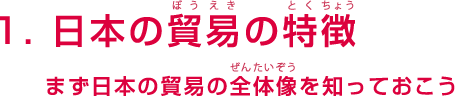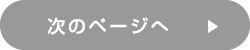![]()
日本は中国、アメリカ、ドイツに次ぐ世界第4位の「貿易大国」です。貿易(輸出入)は、国内外の経済動向や産業の構造変化などによって、取り引きされる品目が変化します。
日本は資源がとぼしく、原油などの燃料資源や工業原料などの大部分を海外から輸入して、それを加工・製品化して輸出する加工貿易を得意として経済成長を遂(と)げてきましたが、日本の貿易構造はさまざまな変遷(へんせん)を経て今日にいたっています。
戦後は、原材料・素材加工型製品、軽工業・雑貨品の輸出が中心でしたが、その後、1960年代は鉄鋼(てっこう)、船舶(せんぱく)など重化学工業が発展し、重厚長大型(じゅうこうちょうだいがた)産業製品が輸出の主力となりました。70~80年代は、日本産業の競争力が大幅に高まり、電子・電気機器、輸送機器、精密機器など加工組立型製品の輸出が主力となりました。80年代の日本の高度成長期の時代には、貿易不均衡(ふきんこう)による貿易摩擦(まさつ)が継続的(けいぞくてき)に生じるようになったことなどから、日本メーカーの海外進出、海外現地生産が積極的に進められました。90年代に入ると、自動車やIT(Information Technologyの略:情報技術)などの高度な技術力や知識力を必要とする高付加価値のハイテク製品をめぐる競争時代となりました。21世紀に入ると、経済グローバル化時代を迎え、バイオ(バイオ・テクノロジーの略:生物工学)や太陽光発電などの新エネルギーなど新たな産業分野も生まれ、産業・ビジネスの環境はめまぐるしく変化しました。さらに中国など新興国(しんこうこく)の台頭(たいとう)や各国間での自由貿易協定(FTA)の締結(ていけつ)など、新たな競争時代を迎えています。そして今、新型コロナウイルスの感染拡大の影響などにより、日本の産業・貿易構造は転換期(てんかんき)に直面しています。
このような産業・貿易構造の変遷(へんせん)の中で、貿易で取り引きされる品目や貿易相手がどのように移り変わり、輸出入の貿易総額が100兆円を超えるまでにいたったのか、貿易の推移を見てみましょう。
- 2021年、日本の貿易総額(輸出額と輸入額の合計)は約168兆円。この金額は日本の国家予算(2021年度一般会計約106.6兆円)を大きく上回っています。
- 日本の貿易総額は、約40年前(1980年)に比べて約2.7倍となっています。
2010年まで過去30年間ずっと輸出額が輸入額を上回って貿易収支は黒字が続いていましたが、2011年に31年ぶりに輸入額が輸出額を上回って貿易収支は赤字となり、以降、2015年まで連続して貿易赤字が続きました(2015年は約2.8兆円の赤字)。2016年に6年ぶりの黒字となり、2021年は2年ぶりの赤字となりました。 - 貿易は、国内外の経済動向や産業構造、ライフスタイルや価値観の変化の影響を受けて取り扱われる品目が変化します。
- 日本の貿易額は、輸出で2007年に、輸入で2008年に最高額を記録しましたが、2009年には、アメリカに端(たん)を発した「金融危機(リーマンショック)」の影響から、100年に一度といわれる「世界同時不況」に見舞(みま)われ、輸出・輸入ともに、これまでになかった大幅な減少となりました。2010年に回復したものの、2011年以降、東日本大震災、EU諸国の政府債務(さいむ)問題による景気悪化、タイの大洪水による生産活動低迷、尖閣諸島問題(せんかくしょとうもんだい)による日中関係悪化などの影響から輸出が再び減少しました。一方、大震災後に一時停止した原子力発電を代替(だいたい)するための火力発電用LNG(液化天然ガス)を中心に輸入が大幅に増加し(2014年には最高額を記録)、貿易収支は赤字基調に転じました。2014年の秋以降、原油などの資源価格の下落などにより輸入が減少に転じ、新興国の成長鈍化(どんか)や国内製造業の海外生産シフトなどで輸出も伸び悩みましたが、2016年は資源価格が引き続き下落したことにより輸入が大幅に減少し、6年ぶりに貿易黒字となりました。2017年も黒字でしたが、2018年は資源価格の上昇などで輸入が増加、2019年は米中貿易摩擦(まさつ)の影響もあり輸出が減少し、再び赤字になりました。2020年は、新型コロナウイルスの影響で輸出・輸入ともに大幅に減少しましたが、収支は黒字になりました。2021年はエネルギー・資源価格の高騰で収支は2年ぶりに赤字になりました。
2021年の日本の貿易総額(輸出額と輸入額の合計)は、約30年前(1990年)と比べると約2.2倍、約40年前(1980年)と比べると約2.7倍に成長しています。ただし、貿易は、国内外の経済動向などに影響を受け、大幅に伸びることもあれば、落ち込むこともあります。
【図1】日本の貿易額(輸出と輸入)の移り変わり(1980年-2021年)
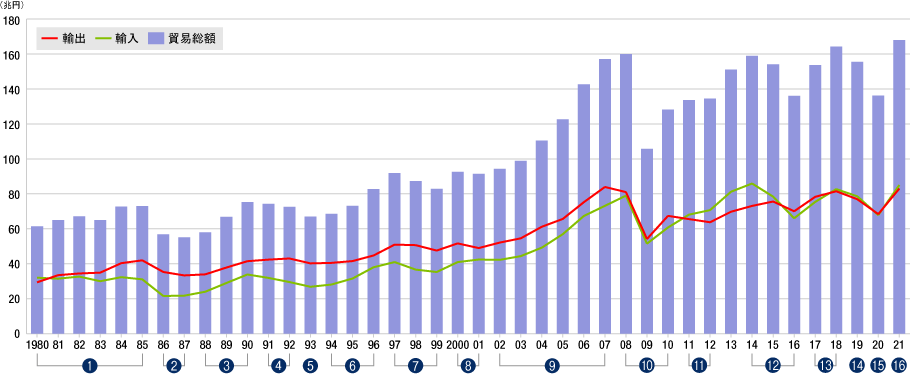
出典:財務省
日本は、世界の中でつねに上位に位置する貿易大国であり、経済大国でもあります。これほどまでに豊かになった日本ですが、かつては第二次世界大戦により大きなダメージを受けました。その後、戦前から培(つちか)ってきた工業製品をつくる高い技術力を活かし、製品をつくるために必要な原料や資源を輸入し、世界に販売・輸出できる製品づくりに国民が力を合わせてがんばってきた結果、高度成長を成し遂(と)げ、今日があります。
2021年、日本の貿易総額(輸出額と輸入額の合計)は約168兆円。この金額は日本の国家予算(2021年度一般会計約106.6兆円)を大きく上回る金額です。前述の図1を見ても分かる通り、貿易額は、国内外のさまざまな経済動向や産業構造の変化などの影響を受けて増減を繰り返し、それぞれの局面(きょくめん)を乗り越えて、これほどの大きな規模に拡大するまでになりました。21世紀に入り、経済グローバル化時代を迎え、貿易環境はめまぐるしく変化し、そして今、新型コロナウイルスの感染拡大などの影響で日本の産業・貿易構造は転換期(てんかんき)に直面しています。
たとえば、【図1】の貿易額が変化したポイントは!
- ①1980年~1985年:自動車やエレクトロニクスなどの付加価値(ふかかち)の高いハイテク製品の輸出が増えて、国内が好景気となり輸入も増えた時期。
- ②1986年~1987年:円の価値が世界的に上がる円高となったため、輸出商品の外国通貨建ての販売価格が上がってしまい、輸出産業が不振(ふしん)となって国内経済が落ち込み、それにともない工業原料の使用量が減り、輸出も輸入も減ってしまった時期。
- ③1988年~1990年:土地・不動産などの価格が異常に上がりつづけたバブル経済による好景気で輸出も輸入も増えた時期。
- ④1991年~1992年:土地・不動産などの価格が急激に落ちたバブル経済崩壊(ほうかい)による不景気で輸出も輸入も減ってしまった時期。
- ⑤1993年:アメリカ、EU、ロシアなど世界的な不況で輸出も輸入も低迷した時期。
- ⑥1994年~1996年:為替レート(1995年79.75円/ドル)の影響により輸入が増えた時期。
- ⑦1997年~1999年:1997年にアジア通貨危機が起こり、輸出は東アジア向けが減ったものの欧米向けが増え、国内の不況によって輸入が減った時期。
- ⑧2000年~2001年:世界的なITバブルの崩壊(ほうかい)により輸出が減る一方、製造業の海外移転などで輸入が増えた時期。
- ⑨2002年~2007年:さらに円安により輸出が大幅に増加し、国内景気が大幅に上向いて輸入も大幅に増加した時期(いざなみ景気)。
- ⑩2008年~2010年:2009年はアメリカ発の金融危機の影響を受け、100年に一度といわれる世界的な経済大不況となり輸出も輸入も落ち込み、2010年はその反動もあり景気が回復の方向に向かい輸出も輸入も回復した時期。
- ⑪2011年~2012年:東日本大震災、EU諸国の政府債務(さいむ)問題による景気悪化、タイの大洪水による生産活動低迷、尖閣諸島問題(せんかくしょとうもんだい)による日中関係悪化などの影響から輸出が再び減少した時期。一方、大震災後に一時停止した原子力発電を代替(だいたい)する火力発電用LNG(液化天然ガス)や原油の輸入が大幅に増加した時期。
- ⑫2014年~2016年:アメリカはゆるやかな景気拡大が続いたものの、中国の減速や新興国の停滞(ていたい)による影響で世界経済は横ばいとなり、輸出が伸び悩んだ時期。一方、原油等の資源価格の下落を主な要因として輸入が大幅に減少した時期。
- ⑬2017年~2018年:中国経済の成長を背景に輸出が増加し、資源価格の上昇により輸入も増加した時期(2018年の貿易総額は過去最高の164兆円)。
- ⑭2019年:米中貿易摩擦(まさつ)の激化により世界的に貿易が縮小し、輸出も輸入も減少した時期。
- ⑮2020年:新型コロナウイルス感染拡大により、世界的に貿易が減少したことから輸出も輸入も減少した時期。
- ⑯2021年~:世界経済の回復を背景に輸出入が増加し、特に輸入はエネルギー・資源価格の高騰で大幅に増加(2021年の輸出は前年比21%増の83.1兆円、輸入は前年比25%増の84.8兆円となった)。
現在、「ヒト、モノ、カネ、情報」などが国境を越えて地球規模で自由に行き交う時代になりました。このため、政治的・経済的・文化的な影響が地球のいたるところで同時に現れるという状況になっています。これが〝グローバリゼーション〟=「世界規模化」です。この流れにより貿易の内容も変化してきています。以前の日本の貿易といえば、モノの輸出入(財貿易)が主でしたが、グローバリゼーションの進展によって、サービス貿易(輸送、旅行、通信、建設、保険、金融、情報などの取引)や、海外の企業を買ったり(買収)、海外で会社を設立して工場を建てたりするなどの「直接投資」が増えてきています。
世界のGDP成長率推移
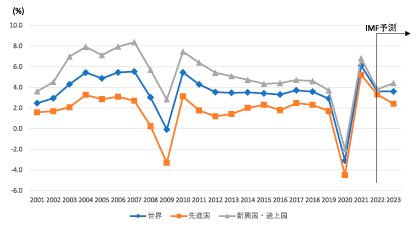
出典:IMF World Economic Outlook(2022年4月)
世界の貿易量伸び率と実質GDPの伸び率の比較
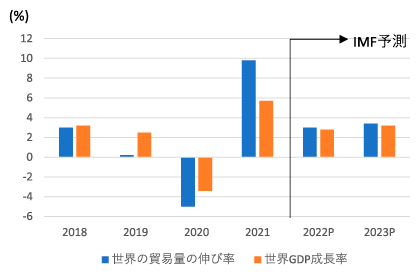
出典:WTO世界貿易見通し(2022年4月12日)
サービス貿易の貿易全体に占(し)める割合推移
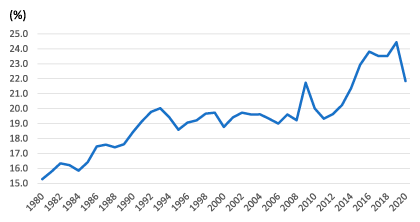
備考:輸出額ベース
出典:WTO統計
直接投資の推移
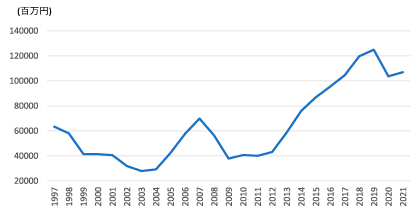
出典:日本銀行