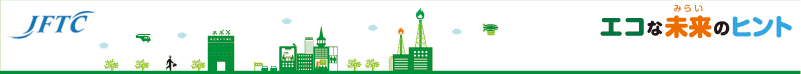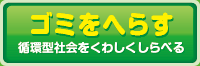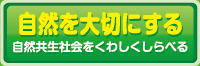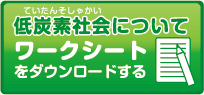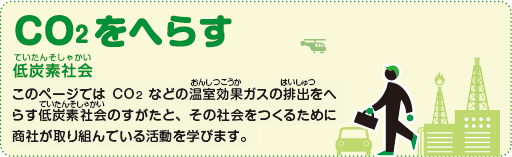世界の国々では電気をつくるときに、そのほとんどを石油、石炭などの化石燃料(かせきねんりょう)を使用する火力発電所(かりょくはつでんしょ)で行っています。しかし、火力発電所はたくさんのCO2を排出(はいしゅつ)することから、地球温暖化(おんだんか)を進める原因になっています。商社は、世界で増加しつづける電気の使用量に対応(たいおう)するため、CO2の排出がない、あるいは少ないクリーンなエネルギーによる発電を世界中で進めています。

バイオマス〔生物体〕発電とは、廃棄物(はいきぶつ)や農作物などからつくられるバイオマス燃料(ねんりょう)を燃やして、発電機(はつでんき)をまわして電気をつくる方法です。バイオマス燃料にはさまざまな原料があり、廃棄物では家畜(かちく)の糞尿(ふんにょう)、住宅廃材(じゅうたくはいざい)や間伐材(かんばつざい)などのあまった木材、家庭から出る生ゴミや廃油(はいゆ)など、農作物ではサトウキビやトウモロコシ、菜種(なたね)、大豆などが使用されます。日本のバイオマス発電では、おもにあまった木材や家畜の糞尿などが燃料として使われており、1家庭の1日分の電力なら牛3頭の1日分の糞尿でつくることができるとされています。

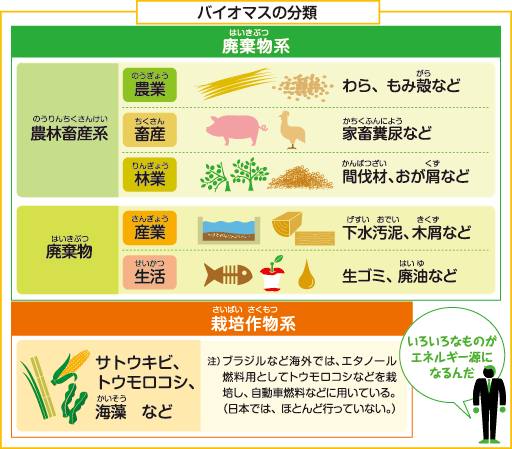
バイオマス燃料(ねんりょう)は発電だけでなく、サトウキビやトウモロコシ、木材などからつくられるアルコールであるバイオエタノールや、家庭の使用済み食用油などからつくられるバイオディーゼルなど、輸送(ゆそう)用の燃料としての利用も増えてきています。
日本ではバイオマス燃料の利用を増やすよう、農林水産省(のうりんすいさんしょう)や経済産業省(けいざいさんぎょうしょう)などの省庁(しょうちょう)が協力して、バイオマス・ニッポン総合戦略(そうごうせんりゃく)を進めています。2010年度の目標として、308万キロリットルのバイオマス燃料を利用し、そのうち50万キロリットルを輸送用(ゆそうよう)の燃料(ねんりょう)とする目標を立てています。これによりCO2を日本の温室効果(おんしつこうか)ガス削減(さくげん)目標の約10%にあたる、760万トンへらすことができます。
ちなみに、自動車用の燃料としてガソリンとまぜて使用されるバイオエタノールは、サトウキビ1トンから0.2トンつくることができます。
商社では、建築現場(けんちくげんば)で出るあまった木材、紙などを燃やして電気をつくるバイオマス発電を行っています。バイオマス発電でつくられた電気は、電力会社に売られるほか、環境に対する取り組みに積極的(せっきょくてき)な企業(きぎょう)で使用される電力などにも利用されています。
また商社は、バイオマスから輸送(ゆそう)用の燃料(ねんりょう)をつくる事業(じぎょう)も行っています。たとえば、農作物では、南米においてサトウキビからバイオエタノールを生産し、ガソリンと混ぜてバイオガソリンとし、輸出(ゆしゅつ)・販売までを行う事業を進めています。ここでつくられたバイオガソリンは、日本にも輸出されています。また、燃料となる植物の品種改良(ひんしゅかいりょう)や農園(のうえん)の開発などにも取り組んでいます。
廃棄物(はいきぶつ)では、下水の汚泥(おでい)、食品廃棄物、産業廃棄物などからガスをつくり出し、燃料として供給(きょうきゅう)するバイオガス事業や、木造住宅の解体(かいたい)やリフォームのときに出るあまった木材等を使って、バイオエタノールをつくる事業などを行っています。
このように商社は、世界中でさまざまなバイオマス事業を進めることで、資源の有効活用(ゆうこうかつよう)とCO2の削減(さくげん)に力をそそいでいます。

バイオエタノール工場(ブラジル)

バイオマス発電所(日本)