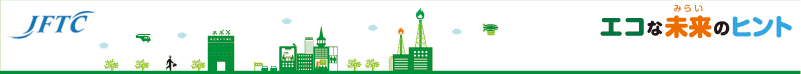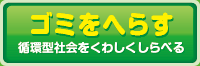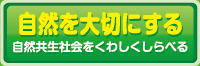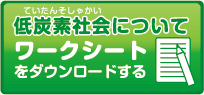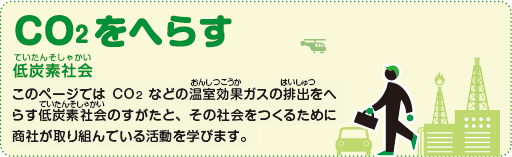世界の国々では電気をつくるときに、そのほとんどを石油、石炭などの化石燃料(かせきねんりょう)を使用する火力発電所(かりょくはつでんしょ)で行っています。しかし、火力発電所はたくさんのCO2を排出(はいしゅつ)することから、地球温暖化(おんだんか)を進める原因になっています。商社は、世界で増加しつづける電気の使用量に対応(たいおう)するため、CO2の排出がない、あるいは少ないクリーンなエネルギーによる発電を世界中で進めています。

燃料電池(ねんりょうでんち)とは、水素と酸素を使って電気をつくり、排出(はいしゅつ)するのは水のみというクリーンな発電装置(はつでんそうち)で、電気と同時に発生する熱も利用することができます。また、電気を送電(そうでん)するときに起こる電気の消失(しょうしつ)もほとんどない良さがあります。ただし、水素はとても軽いために地球上にそのままのかたちでは存在せず、水や石炭、石油、天然ガス、バイオマスなどから取り出す必要があります。
燃料電池は、発電所(はつでんしょ)にかわる大きな発電から、パソコンや家電製品などの電源(でんげん)まで、さまざまな用途(ようと)が期待(きたい)されています。現在は家庭用の発電装置「エネファーム」が販売され、家庭で必要とされる電力の4~6割をまかなえるほか、発電時の熱を利用してお湯をわかすことができます。
このようにたくさんのメリットがある燃料電池ですが、普及(ふきゅう)するには、燃料電池の寿命(じゅみょう)を長くすることや、発電効率(はつでんこうりつ)のアップ、小型化など改良(かいりょう)しなければならない点が多くあります。何よりも購入に200万円近く※かかるため、価格を下げることがいちばんの課題(かだい)です。
※2009年12月現在 国からの補助金(ほじょきん)140万円を利用した場合

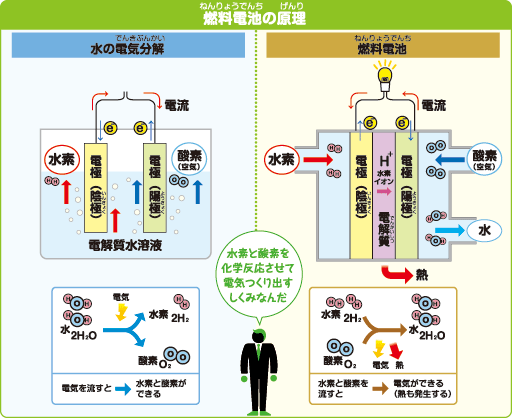
家庭用の発電装置(はつでんそうち)とならんで、燃料電池(ねんりょうでんち)の活用方法として期待(きたい)されているのが燃料電池自動車です。水素を燃料として化学反応(かがくはんのう)を利用して電気をつくり、モーターを動かして走るクリーンな自動車で、東京では試験的(しけんてき)に燃料電池で走るバスの運行(うんこう)なども行われました。燃料電池自動車はCO2を出さないので、排気(はいき)ガスによるCO2の増加もなくなり、地球温暖化(おんだんか)のストップに大きく貢献(こうけん)できます。自家用車としての普及(ふきゅう)は2015年以降といわれており、現在のガソリンスタンドにかわる水素を補給(ほきゅう)する水素スタンドの整備(せいび)や、長い距離を走るために水素を圧縮(あっしゅく)して貯蔵(ちょぞう)しておく特別なタンクの開発などが課題(かだい)となっています。